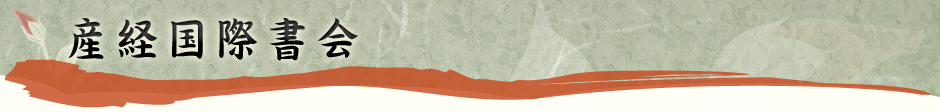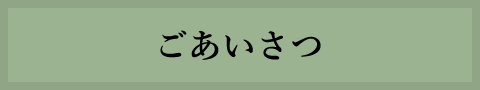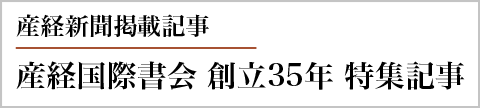2013年6月 3日
[55]産経国際書会参与・久保翆雪さん(87)

58歳で出発、ようやく自分の字が

小林は、変体仮名などは一切使わず、仮名はわかりやすい現代の言葉、文字を用いた。書に厳しい小林が「いい」と言うまで久保は書き直した。天性のものがあったのだろう、入門して3年後には漢詩の手本を書いていた。
だがそれ以上に難しかったのが自分の書作りだ。師の顔がちらつき、苦しみながら書いてきた。だがいまは違う。自分の思いを素直に出す。新春展の出品作「残照」がそうだ。自宅マンションから見える夕日の燃えたぎる熱さを久保は書にした。紙幅からあふれんばかりの濃墨の作品は、沈む夕日は寂しいものではなく存在感あるものとして迫ってくる。そして久保はいま以上に上を目指す。「まだ伸びる。書ける間はまだ伸びしろがある」。そう信じている。(柏崎幸三)
前の記事 : [54]産経国際書会顧問・五十嵐光子さん(88)
次の記事 : [56]産経国際書会顧問・宮崎春華さん(86)